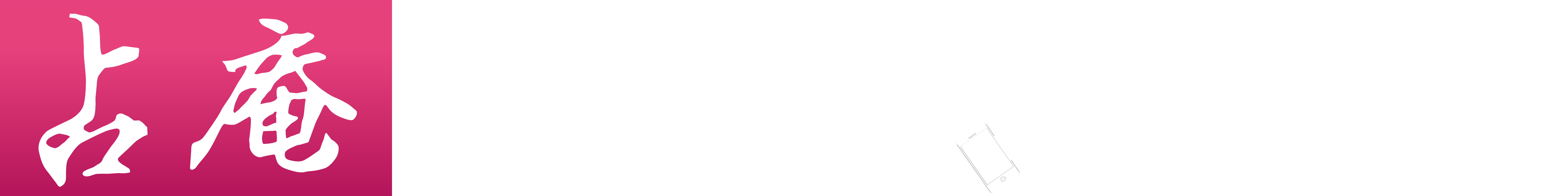宿曜経(文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善悪宿曜経)二十七宿
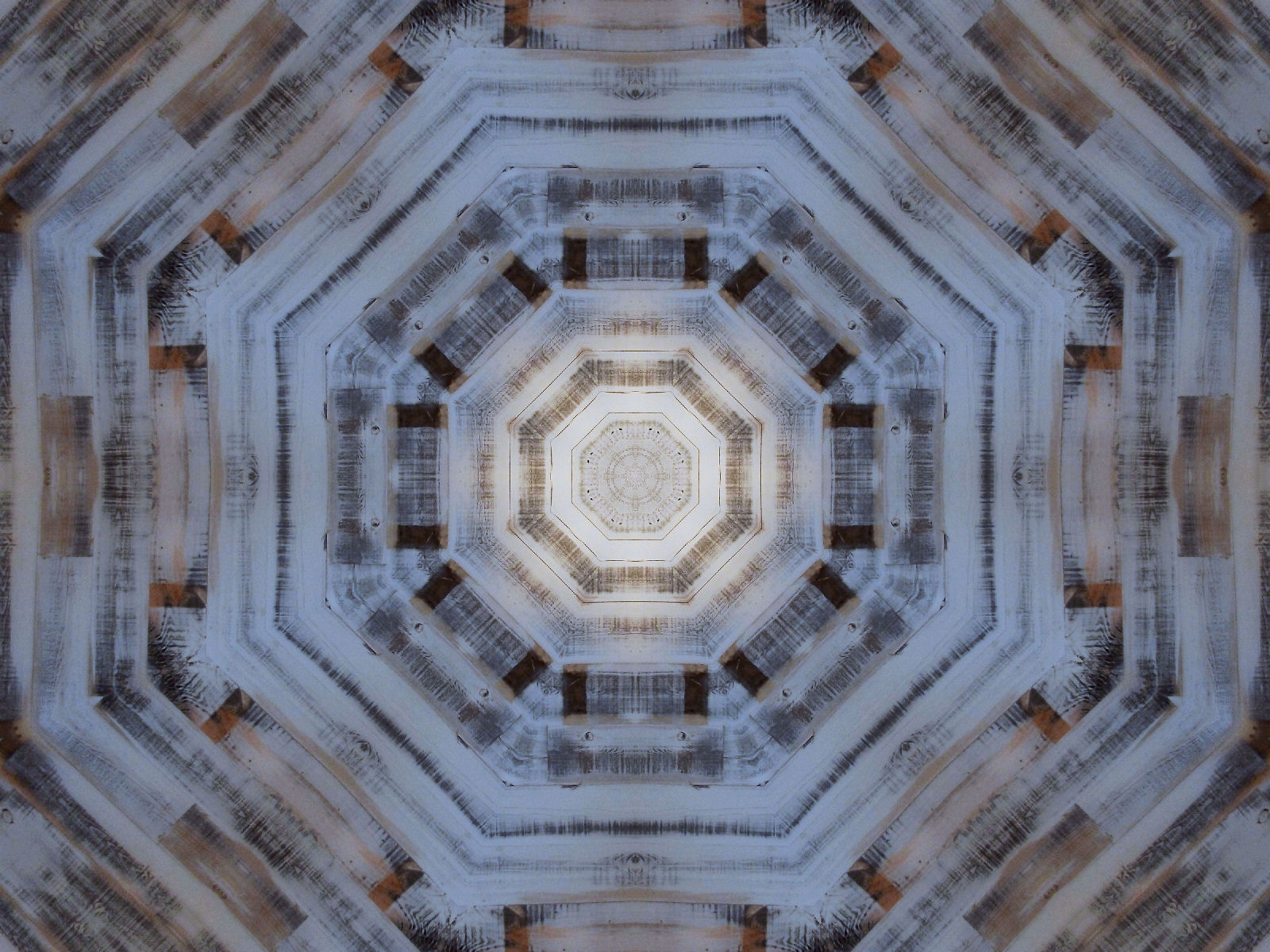 宿曜経は正式には
宿曜経は正式には
「文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善悪宿曜経」
(もんじゅしりぼさつしょせんしょせつきっきょうじじつぜんあくしゅくようきょう)といいます。
長い名前なので宿曜経と一般に呼ばれています。
約3000年ほど前のインドで、知恵の菩薩として知られる
文殊菩薩が28宿を基にした暦を作り「宿曜経」にしたとされています。
その後、インド密教占星術に取り込まれます。
そして仏教を学びにインドに渡った「不空三蔵」が
中国に持ち帰り、書物としてまとめさせた経典が
「文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善悪宿曜経」と
名づけられ、中国宿曜道として発展しました。
日本には、弘法大師「空海」が、日常の生活・行動に積極的に宿曜占星術を取り入れ、弟子達にも教え・広めました。
それは陰陽師の『陰陽道』と人気を二分するまでになり、『宿曜道』と呼ばれることもあり、社会的地位を確立していきました。
宿曜経は、あまりの的中率の高さに江戸時代、徳川幕府は宿曜占星術を封印したこともあるほどです。
明治以降に宿曜占星術は見直され、近年再び注目を浴び始めています。